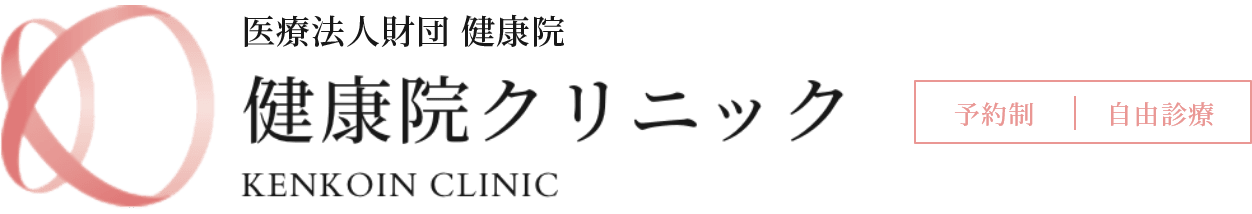新着情報
尿酸とプリン体
猛暑が続き、冷えたビールのおいしさが際立つ時期です(ビール好きの方には)。ビールと言えばプリン体が気になる方も多いと思います。プリン体は痛風のもとにもなる尿酸の原料となる物質であり、プリン体を減らした発泡酒もいろいろあります。プリン体と尿酸についてはいろいろなところで取り上げられていますが、あらためて、少し述べさせていただきます。
プリン体は一つの物質ではなく、プリン環という構造をもつ物質の総称です。DNAやRNAなどの核酸、ATPなどのヌクレオチド、アデノシンのなどのヌクレオシド、プリン塩基など多くのものが含まれます。これらの物質は細胞分裂や代謝などで広く使われます。実は身体の中のプリン体のうち、食品由来のものは約20%であり、約80%は体内で生成されています。食品としては細胞分裂が盛んな肝臓(レバー)や代謝が活発な筋肉(肉や魚介類)にプリン体が多く含まれています。例えばあん肝60gには400㎎のプリン体が、サンマ・イワシには1匹で180~220㎎のプリン体が含まれています。それに対して缶ビール1缶(350mL)に含まれるプリン体は15㎎であり、意外と少ないのです。ただし、アルコールは体内でプリン体を増やしたり、尿酸の排泄を抑えたりする作用を持っています。アルコール量として適量の範囲である500mL以下のビールであれば尿酸値への影響は少ないと言ってよいでしょう。なお、プリン体の一日摂取量は400㎎までがよいと言われていますので、一緒に食べる食品の種類と量には要注意です。アルコール飲料のなかではビールに含まれるプリン体は日本酒、ワイン、蒸留酒よりは多く、紹興酒のプリン体はビールよりも多いようです。
血液中の尿酸が増えると関節内で尿酸の結晶が形成され、炎症を起こして痛風が発症することがあります。関節としては足の親指に付け根が最も多いところですが、他の関節にも起こりえます。血液中の尿酸が増えた状態(高尿酸血症)は痛風だけではなく、尿路結石や腎機能障害、さらには脳や心臓などの血管病との関連も注目されています。
血液中の尿酸濃度は、プリン体からの産生量と体外への排泄量で決まります。プリン体にはさまざまなものがありますが、プリン体の大元になる五炭糖のリボースは果糖から作られますから、果物の摂りすぎにも注意が必要です。プリン体が代謝されて尿酸ができる最終ステップにはキサンチンオキシダーゼという酵素が働きます。高尿酸血症の治療薬のうち尿酸生成抑制薬はこの酵素を阻害することで働きます。一方、肥満の程度が進むほどこの酵素活性が上昇し、尿酸が生成されやい状態になります。肥満はその原因となる食生活でのプリン体摂取過剰とともに高尿酸血症を起こしやすい状態を作っています。
尿酸の排泄はその名のごとく腎臓から尿への排泄が最も多いのですが、これは全体の約3分の2であり、残りの3分の1は腸管から排泄されます。腎臓や腸管で尿酸が体外に出ていく時の通り道にあたる分子(トランスポーター)が見つかっており、このトランスポーターの個人差も血中尿酸値の個人差につながります。また、肥満の中でも内臓肥満の場合にはインスリン抵抗性を介して尿酸の尿への排泄が低下すると言われており、尿酸生成の亢進とあわせて高尿酸血症のリスクが高くなります。
尿への尿酸排泄が多くなると尿路結石のリスクが高まります。尿路結石のうち尿酸結節のリスクが高まることはもちろん、尿が酸性に傾くことによってシュウ酸結石もできやすくなります。プリン体が心配な方は水分をしっかり摂って尿量を確保するとともに、野菜も十分に摂ることでなるべく尿をアルカリ化しましょう。海藻、ナッツ、生姜などもよさそうです。